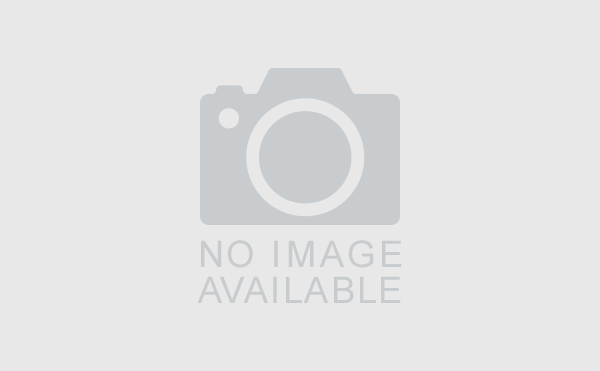江戸川区第2回定例会 3/4 ~ ③終活支援について
安心して暮らし続けるための、いわゆる「終活支援」について
日本総研の2024年の試算によると、配偶者や親族のいない「身寄りのない高齢者」は2050年に約448万人に達し、高齢者の約9人に1人を占める見込みです。老後の施設入居や入院時に求められる身元保証人が見つからないことや、遺体の引き取り手がいないケースが増えることが懸念されています。
介護保険制度の整備により、一人暮らしの高齢者も地域で生活しやすくなりましたが、「自分が亡くなった後、誰が葬ってくれるのか」「お墓には入れるのか」といった不安を抱く方も少なくありません。 エンディングノートを書いても、それを誰かが把握して実行してくれるとは限りません。家族関係の希薄化が進むなか、頼れる人がいない高齢者に対する支援が求められています。
現在、身元保証や通院支援に加え死後の手続きまで支援する民間サービスもありますが、一部には財産の遺贈を契約条件とする業者もあり、実態の把握が不十分です。こうした背景から政府は「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を策定しましたが、金融庁、消費者庁、総務省など7省庁が関与しており、監督官庁が不明確で、拘束力もないことが課題とされています。
横須賀市では、「エンディングプラン・サポート事業」として、収入や資産に制限のある一人暮らしの高齢者等を対象に、生前に協力葬儀社と契約を結ぶ仕組みを導入しています。また、葬儀契約先や終活ノートの保管場所などの情報を、市民なら誰でも無料で登録できる体制も整えています。
足立区では、社会福祉協議会が少額短期保険を活用して、葬儀や家財処分、遺言執行など死後事務全般を支援する「おひとりさま死後事務支援事業」を本年度から開始しました。
本区では、江戸川区社会福祉協議会が「あんしん生活センター」を通じて、高齢者の生活全般に関する相談支援を行っていますが、死後についての支援体制は十分とは言えません。本区でも死後事務を含む生前からの包括的な支援体制が必要だと考え、現状と今後の見解を質問しました。
さらに無縁遺骨の現状と課題についても確認しました。
親族が主体となって弔うことが難しい現実を踏まえ、引き取り手の有無にかかわらず、適切な弔いのあり方を社会全体で考える必要があります。
総務省の2023年の調査では、2021年10月末時点で全国に約6万柱の無縁遺骨が保管されており、その9割以上は身元が判明しているにも関わらず引き取り手がいない状況です。厚生労働省の調査では、こうした遺骨等の扱いに関する明確なマニュアルが「ない」と回答した自治体が約9割に上っていました。
また、身寄りがないと判断されて、火葬・納骨された後、親族の存在が判明し、自治体が謝罪するという事例も起きています。火葬のタイミングやご遺骨の保管などの死亡事務が、自治体に委ねられ、マニュアルやチェック体制の不備から起こってしまったものと考えられます。
本区の場合は、一定の調査の上で親族に引き取り意向を確認し、いない場合は葬祭業者に委託して火葬後5年間遺骨を保管し、それ以降は合祀する対応を取っています。
また、遺留金については、墓地埋葬法や生活保護法では扱われず、民法に基づき、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てる必要がありますが、その手続きに数十万円かかるため、遺留金が少額の場合は申し立てを断念し、自治体がそのまま保管するケースも少なくありません。
引き取り手のないご遺体・ご遺骨に関する現状と課題について本区の見解をただしました。