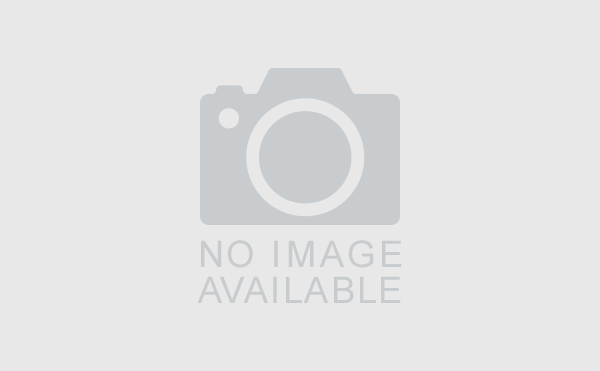あかちゃんポストの課題 ~~こうのとりのゆりかご~~
 所属する福祉健康委員では今年「こうのとりのゆりかご」のある医療法人聖粒会慈恵病院(熊本市)を視察しました。
所属する福祉健康委員では今年「こうのとりのゆりかご」のある医療法人聖粒会慈恵病院(熊本市)を視察しました。
慈恵病院は、1897年(明治30年)に貧困者のための施療院として設立されました。翌年1898年に5人のシスターが到着し島崎村琵琶崎に修道院を創設し、1901年(明治34年)敷地内にハンセン病院「待労院」を作ったことが原型となっています。5人のシスターが最初に行ったことは、ハンセン病者の足を洗うこと(仕えるということ)でした。このことが原点となる精神であり、今でも引き継がれているそうです。


赤ちゃんポストは、2007年5月10日に開設され、2019年には熊本市より特別養子縁組を直接あっせんする事業団体として許可を取得しています。
私たちは外のポストに行き、「3000g程度の赤ちゃんのお人形を抱き、赤ちゃんを抱え、ポストのドアを開け、向こう側に赤ちゃんを置く」という体験をしました。
ドアを開けると、まず、お父さんへ、お母さんへというおたより(カード)があり病院からのメッセージが置かれています。
「考えに考えてここにたどり着いたはず、だけどもう1回考えて!」ということが書いてあるようでした。(片手に抱えた赤ちゃんもずっしり重く、若いお母さんたちのことを思うとつらく感じました)
赤ちゃんを置きに来る人は、最近は両親(実父母)揃ってくる人たち、血だらけでたどり着く女の子、お父さん(実父)などいろいろだそうです。誰かがポストのドアを開けるとすぐに相談体制が取れるように、赤ちゃんのもとへ走る人、来た人の所へ走る人と二手に分かれて受け入れ態勢をつくっているそうです。
慈恵病院に対する社会の目も変わってきたというお話もありました。開設した当初は、「赤ちゃんを捨てるなんて!」「ポスト?ってどういうこと?」という育てることが出来ない親を責め、その手助けをする病院を避難することが多かったそうですが、最近は、「せめて赤ちゃんが助かるのなら」と、好意的な意見に変わってきているということでした。
今年18年を経て、こうのとりのゆりかごの検証は第6期となり報告書が公表されています。
その中で、子どもの出自(しゅつじ)についての報告がありました。
「児童の権利に関する条約」第7条第1項において、子どもが出自を知る権利はできる限り保障しなければならないと規定されており、2016年に改正した児童福祉法においても「こどもを権利の主体と据え、最善の利益を優先すべきことが明確化されたこともあり、匿名性に重きを置いたゆりかごの運用は、こうした子どもの権利を損なうことにもつながりかねず、ゆりかごの仕組みに限界があると言わざるを得ないというものです。
どうしたらいいのでしょうか?
「最後の砦」となり、「匿名にできるから、ゆりかごに預けに来た」という事例も複数あります。
匿名に出来なかったら、その赤ちゃんは生まれてこれなかったかもしれません。一番近くにいるはずの大人である親に話せない、「話すことが出来ない」「理解を求められない。」というのが理由のようです。
親子の関係が築けない中で、妊娠したことを口にできない状況や気持ち、子どもの権利や成長した子どもの気持ちを、私たち周囲の大人はどのようにサポートできるのでしょうか?
東京でも、墨田区に「ベビーバスケット」と名付けて「赤ちゃんポスト」が今年4月に開設されました。慈恵病院と同様に、匿名で子どもを預かる「内密出産」も開始しています。開設1か月ですでに赤ちゃんが預けられていました。「一人で悩まずに相談してほしい」と関係者はいいますが、当事者に支援の声が届きにくいのが現状だと、改めて思いました。
SNSでも電話相談でも、相談する手段はいろいろありそうですが、一人で悩む赤ちゃんを置きにくる当事者、望まない妊娠をした当事者などにとっては、誰かに相談するということすらハードルになっているのかもしれません。
当事者である若者に寄り添うとは、どういうことなのでしょうか?
周知の手段を増やす?当事者が「助けて」と言える社会とは?
女性ばかりが追い込まれてしまう社会、子どもを育てることが難しい社会となってしまっている今の日本の社会に憤りを感じます。女性が悲しまない社会にすることが求められていると考えます。
すぐできることは、相談窓口があることが当事者に届くように、多種にわたる発信をすることなどがあると思います。
時間をかけて行えることは、男女にかかわらず自分の身体について幼少のころから「正しく知る事」の機会を作ることがあると思います。
人として生きていくうえで大切な「性」について、「命」について、義務教育の間に学ぶ機会が必要だと考えます。生活者ネットワークは、指導要領を超えて、包括的性教育「国連のセクシュアリティ教育ガイダンス」を教育に取り入れていくことを要望しています。
学齢に合わせて継続的に行っていくことが重要だと思います。